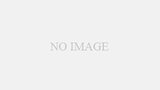表札と門札は違います

表札には、門の横に掛ける【門札】と、玄関ドアの横に掛ける【表札】があります。
ところで表札(ひょうさつ)と門札(もんさつ)を混同される方が非常に多いようですが、厳密にはいくつかの違いがあります。
- 掛ける場所
- 役割
- 適した素材
以上の3つになります。
それでは具体的な解説をさせていただきます。
門札とは
【門札】は、その家・家族・先祖代々の敷地の入り口である門に掛けることから、【苗字】のみを記せばよしとされています。
家の敷地・土地を表すもので、「~家の土地」を示すものとお考え下さい。
材質は特に気にする必要はなく、外溝や塀等の色、雰囲気に合わせてお選び頂ければ良いでしょう。
基本的には雨風に強い耐久性のある材質の方が無難です。
門札は必ずしも木製にこだわる必要はありません。
むしろ木製の表札は雨風にさらされる場所は不適当なので、当店では「門札」に木製素材はおすすめしておりません。
表札とは
門札に対して、【表札】は当主の姓名(フルネーム)を入れ、その家の持ち主(主人)を明示します。
門札はあまり素材を問いませんが、表札は天然銘木で作って下さい。
国産天然銘木の自然の生気と、エネルギーをたっぷりと含んだ素材で作った表札が一番良いと言えるでしょう。
玄関と密着したものですから、自然素材が良いのです。
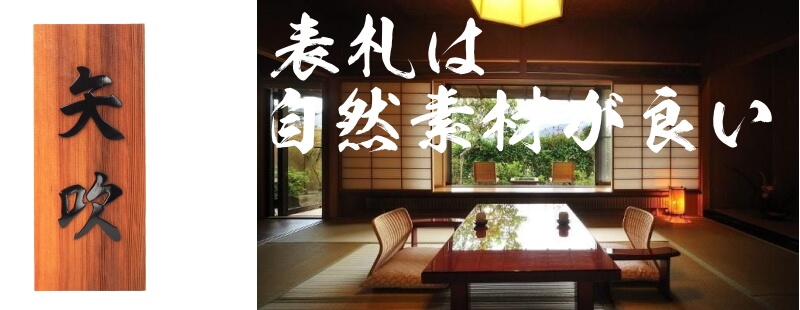
銘木で作った表札は大変美しく、威厳と風格に満ち満ちたその雄姿は、家のランクを格段に上げてくれることでしょう。
表札は、家の顔である玄関に掲げる【玄関の顔】、家の風格を決定付ける大切なものです。
表札を掲げる位置
家相・風水学に於いて、表札は玄関の左側(外から玄関に向かって右側)に掛けるのが一番よいとされています。
和洋で言えば、和風なら左側、洋風なら右側とも言われていますが、基本的にどちらでなくてはいけないと言う事ではありません。
その家の玄関に掛けてみて一番しっくりとくる、自然な方に掛けるのが一番良いでしょう。
分からない場合には左(外から玄関に向かって右)に掛ければまず無難と言えます。
表札の掛ける場所で「凶」となる位置は、
- ドアの表面に直接掛ける
- ドアの真上に掛ける
以上の2点が上げられ、どちらにしても明らかに不自然な掛け方である事はお分かり頂けるかと思います。
大自然の法則により<不自然=凶>なのです。
妻子の名は不要です
表札に彫る名前は、一家の長である主人姓名のみを入れるのが基本です。
妻や子の名前を入れることは、主人から家運を奪ってしまうと考えられています。
- 家の主人の運気が向上することが、家族全員の運気の向上に繋がるのです。
- 女性だけの家などフルネームの表示では防犯上問題がある場合は「姓のみ」でも大丈夫です。
むしろ、女性のみが住んでいる場合は、「姓のみの表札」にして下さい。 - 男性が世帯主の場合でも、「姓のみ」がよろしければそれでも問題はありません。
「姓のみ」の表札が悪いわけではありません。
表札の交換時期
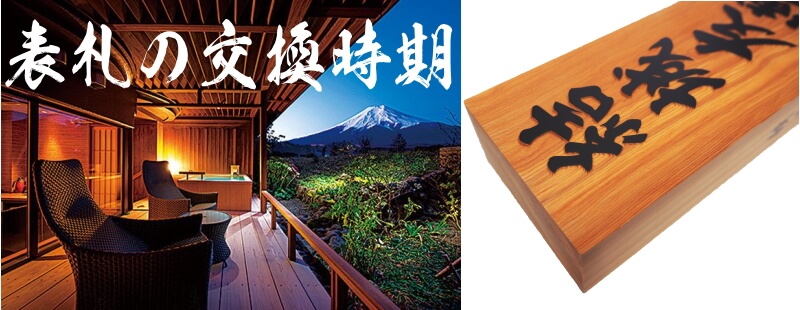
天然銘木は塗料を塗り重ねて防水加工がしてありますが、それでも常に風雨・外気にさらされているため時間が経てばやがて傷みがきます。
天然銘木の表札の寿命は10年(目安)とお考えください。
10年未満であっても、傷みが出てきたと思われる場合には早めの交換が望ましいでしょう。
傷みがひどい表札はとても吉相とは言えません。
気候にもよりますが、早くて5年、最長10年ほどとお考え下さるのがよろしいでしょう。
年数によらず傷みがでましたらお取替えされることをお勧めいたします。
しかし、早めに傷んだ場合にもマイナスなイメージは持たないで下さい。
【縁起物が壊れる時は、難を引き受けてくれた時である】と言われている通り、「家族の表札が難を引き受けてくれたのだ」と、前向きに捉えて対処するのが正しい開運表札の考え方です。
天然銘木に名前を彫る事によりその人の分身となるのですから、身代わりになってくれた表札に感謝し、産土神社でお焚き上げするのが正しい扱いであり、心構えであります。
伊勢神宮も、式年遷宮として20年に一度屋移りします。
表札も印鑑も同様に、生きた素材は生まれ変わりながら開運効果を維持していくのです。